
ラフに生きよう、”わたし"のままで

ひとりじゃないよ みんなここにいるよ
一緒に楽しもうよ

こんにちは、モモ( momohsphss)です。
私は”心理セラピー”を提供しています。いわゆる心理療法、カウンセリングです。
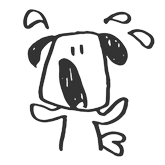
え?なにが違うの?
と疑問に思うかもしれませんね。
ググると定義が出てくるけどさ、定義も表現も人によって違うから混乱するよね。
つまり何をするのか……よく分からん!!!と、ずっと思っています。(今もかよ)
そこでモモちゃんなりに、心理セラピー(心理療法)、心理カウンセリングについて説明してみようと思います。
セラピーを受ける側が理論を詳しく知る必要はないけど、ざっくり違いを把握しておくと自分に合った手法を見つけやすくなります。
一般論に個人的見解を加えているので、人によっては違和感をもつかもしれませんが。あくまで”モモちゃんなりの定義”ってことで、予めご了承ください。
心理セラピー(心理療法)とは、簡単に言えば『心』を使って『心』の苦痛を和らげる手法です。
化学療法では薬物を使い、自然療法では自然界に存在する物質を使うように、心理セラピー(心理療法)では心を使うのです。
補助として道具を使用する場合もあるけど、メインで使用するのは心です。
心理セラピーの手法は多岐に渡り
など……って、これだけだと分かんないと思うので、3大アプローチをご紹介します。

心理セラピーには大きく3つの流派があります。
それぞれ簡単に説明しますね。
精神分析的アプローチは無意識の領域に働きかけます。
頭に浮かんだことを思いつくまま話すことで、抑圧されたトラウマやコンプレックスの発見を目指します。
意識、無意識、エゴ、自我といった言葉は精神分析の領域で登場したもの。
認知行動的アプローチは、できごとが起きたときの反応と行動に焦点を当てます。
「それが起きたとき、どう行動するか」といった客観的に観察可能な行動にアプローチするところが他と違いますね。
認知のゆがみ、自動思考といった”考え方の癖”を把握して、具体的に行動を修正していきます。
人間学的アプローチでは、「人間は潜在的に自己実現と成長本能を備えている」として、条件を整えることで建設的な変容を目指します。
つぎの3つは心理療法に馴染みがない人も耳にしたことがあるかもしれません。
自己治癒力を高めることに焦点を当てたアプローチですね。
私は自分自身が生きづらさを克服した経験から、人間学的アプローチが好きで採用しています。
折衷主義のため臨機応変に必要なものを組み合わせるスタイルですが、とくにお気に入りはナラティヴ・セラピーです。

カウンセリングとは、簡単に言えば話を聞くこと。なので言葉自体は心理業界以外でも、さまざまなシーンで使われています。
心理カウンセリングとは、心理学の理論をベースにしたカウンセリングの手法を使って認知※・行動の変容を促すことです。
この”話を聞く”という行為は、シンプルだけど奥が深く、延々に語れるほど難しいもの。
だってさ、冷静に考えたら話を聞くだけで相手の「ものの見方・感じ方・考え方」が変わるって、すごくない??
日常生活で普通に会話してて、自分の価値観がガラッと変わるような気づきを得られる瞬間って、そう頻繁に起こるものじゃないよね。
心理カウンセラーは何も考えず「聞いてるだけ」に見えて、実はめちゃくちゃ頭を使っているんですよ。
って、余談でした💦
一昔前と比べれば、心療内科や心理カウンセリングの利用が身近なものになったとはいえ
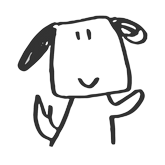
心理カウンセリングって、病んでる人が話を聞いてもらうやつでしょ?
というのが一般的なイメージかと思います。
実際には、健康な人も利用するし、悩みの深さも範囲も幅広くあります。
問題が顕在化している人もいれば、健康診断のようにメンテナンスの一環として受ける人もいます。
など
また形態によっても利用する人の雰囲気が変わりますね。
より深い部分の話をじっくりしたい人は1対1の個人カウンセリング、その場の空気感から得たいものがある場合はグループカウンセリングなど。
目的によって使い分ける人もいます。
心理カウンセリングを有効活用するには一定の条件があり、状況によっては利用できないので注意してくださいね。
とくに日常生活に支障が出るほど深刻な場合は、薬物療法や休養が優先されるので、カウンセリングを受けられません。これは医療機関であろうと、個人開業であろうと一緒です。
など
心理カウンセリングは短くて45分、長いと120分ほど集中して話す必要があります。これだけでも一定の体力・気力を使います。
さらにカウンセリングの手法は会話をベースにしたものが多いので、会話で一定レベルの意思疎通ができないと成り立たないんですよね。
とはいえ流暢に話す必要はなく、まとまってなくても、どもって言葉につまっても大丈夫。そこは心配無用です。
また医療機関を受診している場合、医師の治療方針に沿って対応する必要があるため、かかりつけ医院以外では利用を断られる場合もあります。

ここからはモモちゃんが感じている、心理セラピー/カウンセリングのメリット・デメリットの話です。
心理セラピーやカウンセリングのメリットは、問題の根本的な部分から変えられること。
表面化した現象に対処するだけでなく、自己治癒力から高めることができます。
風邪でいえば、そもそも風邪を引かないように免疫力を上げるとか。もし風邪を引いても悪化しないように自分で対応できるようにするとか。
こうして根本的な部分にアプローチすることで、応用力が身につくこともメリットだと感じます。
心理セラピーやカウンセリングのデメリットは、薬物療法に比べて時間がかかること。
数週間から数か月で大きな変化が見られる場合もありますが、数年単位の長期的な目線で継続が必要なケースもあります。
薬のように「1回飲んだら数時間で痛みが消える」といったものではないため、腰を据えて取り組む必要があります。
また内面の変化は見えず主観に頼る部分も多いため、客観性を重視する人にとっては曖昧に感じてデメリットになるかもしれません。
モモちゃんが心理セラピーを取り入れたのは、16歳で適応障害になり、薬物療法を4年間続けて一時的に回復したものの、環境が変わって再発した経験があったから。
薬がラクにしてくれるわけじゃない。自分が変わらなければ、この苦しさは一生続くんだ。
そう思って、根本的なところから変わると決意して、心理セラピーに取り組みはじめました。
たしかに本当の意味で「終わった」と感じたのは、はじめてから7~8年ほど経ったころ。
だけど徐々に上向きになっているので。
最悪の状態から脱したのは薬物療法を続けたのと同じくらいの期間で、4年くらい経ったころでした。
これだけ見ると”長い”と感じるかもしれないけど。
根本的な部分から変わっているので、人や場所といった”環境”が変わっても対応できるし、仕事・恋愛など違うテーマにも応用できます。
かけた時間に比例して幸福感や生きやすさも増加しているので、心理セラピーを選択して良かったと思います。
心理セラピー/カウンセリングは、『心』を使って『心』に働きかけ、健やかな毎日を手に入れる手法です。
興味のある人は取り入れてみてね。
モモちゃんが個人で心理セラピスト(カウンセラー)になった理由は、こちらの記事でお話しています。